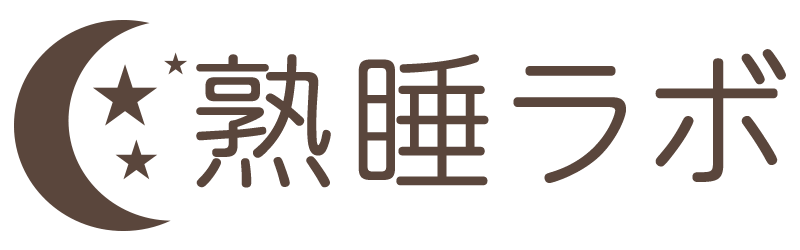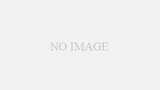私たち人間は脊椎動物であり、日中に活動することで背骨の神経には負担がかかります。
この神経は、睡眠時横になることで休まるのですが、一晩中動かないだけでは神経を十分に休ませることにはなりません。
枕や布団の上でのスムーズな「寝返り」が神経を休め、深い睡眠へと導くのです。
「寝返り」=「寝相が悪い」の?
「寝返りは、寝ている間に動いているから寝相が悪いってことじゃないの?」と思われるかもしれません。
人は一晩に15回~20回寝返りをうつと言われ、寝返りは良い睡眠にとって必要不可欠な無意識の動きなのです。
逆に寝相が悪い状態とは、布団を蹴り飛ばしたり、脚を大きく開いて眠るなど、寝ている際の体のポジションや動きが不適切なことを言い、一緒に寝ているパートナーや家族に迷惑をかけてしまう原因になりがちです。
つまり、寝返りは良い睡眠を促進するための必要な動きであることに対して、寝相の悪さは逆に睡眠の質を損なわせる状態とも言えます。
寝相が悪くなる原因
寝相が悪くなる主な原因としては次のようなものが挙げられます。
- ストレスや不安
- 睡眠環境
- 運動不足
- 飲酒
- 過食
- 夜間の騒音、ノイズ
- 不規則な睡眠スケジュール
ストレスや不安
仕事や家事、勉強などで精神的な負担が高いと夜間に体が不安定になりやすく、寝相が悪くなることがあります。
趣味やストレッチなどストレスを軽減させるような方法はもちろん、就寝前にリラックス効果のあるハーブティーを飲むなど、心も体も落ち着かせてから寝ることもオススメです。
睡眠環境
体に合わないマットレスや枕、部屋の温度が高すぎるまたは低すぎるなど、寝室の環境が不快であると、寝相の悪さの原因になります。
無意識で安定した寝姿勢を探しているうちに、体の向きや位置が変わっていることがあるので、自分にあった寝具を見つけて睡眠環境を整えましょう。
運動不足
日中の活動量が少ないと体のエネルギーが消費されず、夜間頻繁に寝返りを打つなどして寝相が悪くなることがあります。
就寝の3時間ほど前に適度な運動を行うことで、エネルギーが消費されることに加えて寝つきが良くなり、深い睡眠状態を作り出すことができます。これは脳の温度(脳温)に関係があり、脳温の低下が眠気を引き起こしやすくするためです。
睡眠時には脳も休息をとるために脳温が下がっていきます。運動によって脳温が上がっている状態で横になると、温度の変化量が普段よりも多く、よりぐっすりと眠れるようになります。
ただ運動すればよいというわけではなく、習慣的に行うことが快眠への近道です。激しい運動は体が目覚めてしまい逆効果になるので、継続しやすいランニングのような運動がオススメです。
飲酒
就寝前のアルコールの摂取は、睡眠中の不快感を引き起こし、寝相を悪くする原因にも。
過度の飲酒は舌を支える筋肉を緩ませてしまうため気道が狭くなり、取り込まれる酸素の量も減ってしまうので、十分な酸素が体に回らずに脳が酸欠状態になってしまいます。その結果、苦しさから寝相が悪くなることもあるようです。
また同時に、気道が狭くなると鼾(いびき)を引き起こしやすくなるため、一緒に寝ているパートナーへの騒音による睡眠妨害の併発も危惧されます。
さらに、アルコールには血流を良くする作用があり、鼻の血管が腫れて鼻づまりを起こす原因にもなるといった様々な弊害を引き起こしかねないため、就寝前のお酒は控えるのが良いでしょう。
過食
活動量に見合っていない食事量、夜中の間食などは睡眠に影響を与えます。体に余ったエネルギーは寝相を悪くするほかに、使いきれなかったエネルギーが脂肪になり、それが首回りに蓄積して気道の圧迫が起こり二次的に睡眠障害を引き起こすこともあるようです。
また、食事直後の就寝は消化器官の活動による体温増加の影響で質の低い睡眠になりがちです。
消化器官は食べ物が取り込まれれば寝ていようが活動を続けます。脳は横になっていれば徐々に温度が下がっていきますが、消化器官は消化が終わるまで自然に体温を下げることはできないため、体を十分に休められない状態となってしまいます。
体温上昇による影響だけでなく、胃の活動による腹痛や胃食道逆流症による胸やけも寝相の悪さに繋がるため、食事は少なくとも就寝前の2時間前までに済ませておきましょう。
夜間の騒音、ノイズ
環境音やパートナーのいびきなど、外部の騒音が睡眠を妨げ、寝相を悪くすることがあります。自身は気にせずに寝られているつもりでも、知らないうちにストレスが少しずつ蓄積して眠りに影響することも。
いびき対策効果が期待される枕や寝姿勢、ひどい場合にはいびきの専門家に相談するなど、解決が可能であれば早めに対応するのに越したことは無いでしょう。
不規則な睡眠スケジュール
夜遅くまで起きている、起きる時間が日によってバラバラなどの生活リズムの乱れは、睡眠の質を下げ、寝相の悪化を引き起こす原因となります。毎日決まった時間に食事や睡眠を摂ったり、適度な運動など意識しながら生活することが寝相の悪さの改善に繋がります。
寝返りの効果
「寝返りと寝相の悪さの違いと原因は分かったけど寝返りってそこまで重要?」と言う疑問にもお答えしますね。
寝返りには以下のような効果があります。
- 日中に歪んだ体をリセットする
- 同じ姿勢で寝る際の、体にかかる負担を和らげる
- 寝具内の空気を入れ替える。睡眠中に発生する熱のこもりや汗の不快感を解消し、心地よい睡眠環境に整える。
しかし、寝返りがスムーズにできないと
- 夜中に何度も目が覚める
- 睡眠が浅くなる
- 寝起きがスッキリしない
というような原因にもなります。
一晩中同じ体勢で寝続けるのは、実際には睡眠の体勢としては苦痛であるのかもしれません。
『自由に寝返りをうてるか』を基準に、現在使用している寝具を再検討することで、睡眠環境を改善させる手がかりになるかもしれません。
睡眠環境の見直しはどこから?
まず手軽なのが、シーツやパジャマなどの寝ている時に直接肌に触れる物です。
たとえばフリースや起毛素材の物は摩擦が大きいため、布団の中で自由に寝返りがしにくくなるだけでなく、寝ている間に暑くなって体温調節が難しくなる可能性もあります。
寒い季節には掛け布団と毛布を併用する方も多いでしょう。
大半の方が毛布を重ねて使用するかと思いますが、どう重ねていますか?実は、掛け布団の上に毛布を重ねるほうが、保温効果が高いのです。
摩擦のある毛布ではなく、シーツが肌にあたることで寝返りも打ちやすくなります。これにより深い睡眠を得ることができるので合理的でいいですよね。
また、重すぎる掛け布団は寝返りを妨げてしまいますので掛け布団の軽さも重要なポイントと言えるでしょう。
枕に関しても、低反発枕のような沈み込みが遅い素材の枕は、寝返りを阻害しやすいため、沈み込みの早い素材、かつ横向き寝でもしっかり頭を支える枕を選ぶことが重要です。
子どもの寝返りは成長に必要なもの
お子さんがよく寝返りを打ち、「うちの子って寝相が悪い?」と気をもんでいる親御さんもいらっしゃるかもしれません。
しかし子どもは「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」のサイクルが頻繁に変わり、大人よりずっと睡眠時間が長いため、比較的寝返りの回数も多くなる傾向にあります。
寝返りをサポートするおすすめ寝具
寝返りをしやすい素材の枕を選ぶ場合、『BlueBlood(ブルーブラッド)』素材を使用した枕がオススメです。
頭を乗せた瞬間スッと沈み込み、それでいてその人に合った高さで支える枕で、寝返りをしても常に適切な高さで支え続けてくれます。
適度な寝返りによる質の良い睡眠は、成長期の子どもたちにはとても重要です。もちろん、日々忙しく過ごす大人にとっても、質の良い睡眠で疲れを溜めないことは大切です。睡眠環境の改善で毎日を快適に過ごしたいものですね。